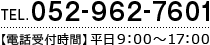特許権
特許について
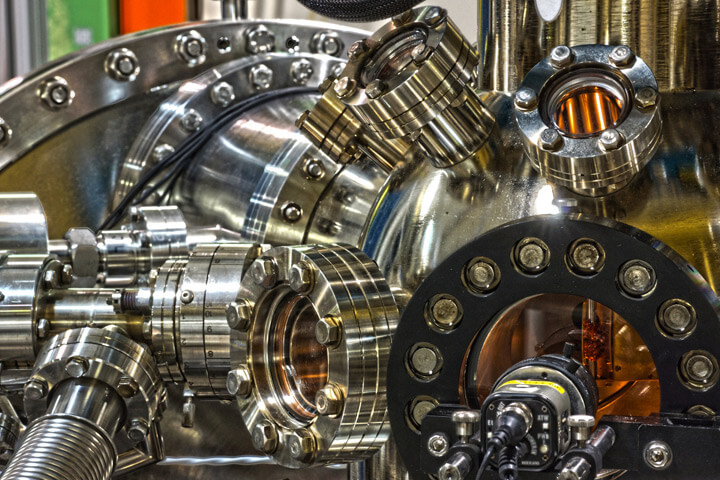
特許制度は、発明の保護と利用を図り、高度な新しい技術のアイデアを一定期間独占実施できる制度です。
特許権の登録要件は、「発明」であって、「新規性」と「進歩性」が必要となります。「新規性」とは、特許出願時において新しいものであることで、例え自ら創作し新しいものだと思っても、何処かで他人が公開しているものであれば新規性はなく特許を取得できません。「進歩性」とは、特許出願時において従来技術から当業者が容易に創作することができないものであることで、単なる公知技術の寄せ集めは特許を取得できません。
登録されると特許権が与えられ、その発明を一定期間独占的に実施できる権利が与えられます。特許された発明を、権原の無い他人が実施すると特許権侵害となり、その他人に対し差止めや損害賠償の請求ができます。
なお、特許権の存続期間は、出願日から20年です。
出願のメリット
特許出願は、ある商品に係わる発明を特許登録し、その商品を独占販売して利益拡充に繋げるためにするのが一般的な考え方です。しかし、他にも、その後の他人による同一発明の特許権の取得を防止したり、他人の同一発明の特許権の有無を調査する手段としても利用できます。
外国出願について
日本の特許権の効力は日本国内に限定されます。日本出願と同一発明を外国でも保護されたい場合には、各国ごとに出願・登録する必要があります。
他国で他社により特許登録されると、その国での自社の使用ができないか、その権利を無効にできるとしても多大な費用と労力を必要とします。国際化が進む中、海外への輸出は事業展開において重要な要素となりますので、自社の製品の方向性を検討し、外国出願が必要な発明かご検討下さい。
当事務所では、米国、アジア、欧州など幅広い国へのコネクションがあり、ほぼ全世界への出願に対応しております。
特許取得の流れ
まずは、内容を確認させていただきます。説明書など関係資料がある場合は、ご提示下さい。アイデアを口頭で説明していただいてもかまいません。 ご訪問も可能ですのでお気軽にご連絡ください。
ご依頼により他社の先願の調査もいたします。
発明内容をお聞きし、資料や調査内容をもとに出願草稿を作成いたします。図面がある場合はご提示下さい。無ければ当方で作成させていただきます。
出願草稿をご検討頂き、その後に出願します。
出願日から1年6ヶ月経過すると出願内容が公開されます。
出願とは別に審査請求書を提出します。
審査請求をしなければ実体審査はされません。審査請求は出願日から3年以内です。
審査の結果に拒絶の理由が発見された場合「拒絶理由通知」が送られてきます。これに対し、意見書や出願内容の補正書を提出し、対応することができます。
審査において、拒絶理由が無いと判断されると特許査定が送られてきます。特許料を納付すると特許権の設定登録がされ、特許証が発行されます。
特許出願及び登録料(特許庁印紙)
| 特許出願 | 14,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 出願審査請求 | 118,000円+(請求項数×4,000円) | ||
| 特許料 | 平成16年3月31日 迄に出願審査請求したもの |
第1年~第3年 | 毎年10,300円+(請求項数×900円) |
| 第4年~第6年 | 毎年16,100円+(請求項数×1,300円) | ||
| 第7年~第9年 | 毎年32,200円+(請求項数×2,500円) | ||
| 第10年~第25年 | 毎年64,400円+(請求項数×5,000円) | ||
| 平成16年4月1日 以降に出願審査請求したもの |
第1年~第3年 | 毎年4,300円+(請求項数×300円) | |
| 第4年~第6年 | 毎年10,300円+(請求項数×800円) | ||
| 第7年~第9年 | 毎年24,800円+(請求項数×1,900円) | ||
| 第10年~第25年 | 毎年59,400円+(請求項数×4,600円) | ||
| 審判(再審)請求 | 49,500円+(請求項数×5,500円) | ||
| 表示変更登録申請(住所、名称変更) | 1,000円 | ||
| 移転登録申請(譲渡) | 15,000円 | ||
詳しくは特許庁の詳細料金一覧を御覧下さい。
上記の他、弊所への手数料が別途必要となります。
弊所の手数料は、内容、難易度によって異なりますので、お客様とのご相談のもとに決めさせていただきます。 詳しくはお問い合わせください。
よくあるご質問
自分で出願したら拒絶理由が送られてきて、どのように対応してよいかわかりません。
その後の対応を依頼できますか?
はい、お受け致します。その際には、意見書・補正書を提出する必要がありますので、当所で作成することとなります。
しかし、出願時の明細書に新たな技術的説明を追加することはできませんので、補正する範囲が制限される場合があり対応できない場合もあります。
そのため、出願時の書類内容、拒絶内容、補正可能範囲等を検討した上で意見書・補正書を作成する必要があります。権利化できるか否かはその作成内容に大きく左右されますので、専門家である特許事務所にご相談下さい。